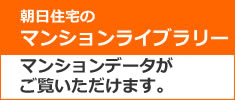相続税の概要と税制改正の影響
こんにちは、税理士の在間です。
今回から複数回にわたって相続税についてお伝えしようと思います。
今回は相続税の概要と税制改正の影響についてです。
Ⅰ 相続税計算の概要
上記のケースが平成27年1月以降の相続であった場合はどのようになるか計算してみます。
相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺した純財産から基礎控除額を差し引いた金額を法定相続分で(仮に)分割し、
分割した金額に応じた税率を適用して相続税の総額を計算し、相続税の総額を各人の取得財産の比で按分して
各人の負担税額を計算するという仕組みになっています。
では、いきなり計算内容からの説明で恐縮ですが、相続税の計算を具体例で見ていきます。
(相続時精算課税制度は選択していない前提です。)
<例>
父が死亡しました。相続人は配偶者である妻と子2人の計3人です。
遺産は以下の通りで、
すべて法定相続分(妻2分の1、子4分の1ずつ)で相続税の申告期限前に遺産分割しました。
なお、金額はいずれも相続税評価額です。
遺産内訳
自宅土地 6,000万円(小規模宅地適用後)
自宅建物 1,000万円
預金 4,000万円
有価証券 4,000万円
合計 15,000万円
債務はありませんでしたが、相続税計算で差し引くべき葬式費用が200万円発生しました。
従って相続した純財産は、
15,000万円-200万円=14,800万円です。
基礎控除額を差し引きます。
金額は、5千万円+1千万円×法定相続人数です。(平成27年1月1日以降開始の相続より、3千万+600万円×法定相続人数に改正されます。)
5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円(基礎控除額)
14,800万円-8,000万円=6,800万円(課税遺産総額)
相続税の総額を計算します。
妻の法定分に応じた相続税額
6,800万円×1/2=3,400万円
3,400万円×20%-200万円=480万円
子の法定分に応じた相続税額
6,800万円×1/4=1,700万円
1,700万円×15%-50万円=205万円
相続税の総額
480万円+205万円×2人=890万円
各自の負担税額(全財産を法定相続分で分割し、葬式費用は法定相続分で負担)
妻 890万円×1/2=445万円
子1 890万円×1/4=222.5万円
子2 890万円×1/4=222.5万円
配偶者の税額軽減により、妻の分の税額はゼロになります。
従って納税額は子2人分で445万円です。
参考:相続税の速算表

平成27年1月1日以降開始の相続より、次のように税率が改正されます。

Ⅱ 税制改正の影響
相続した純財産 14,800万円
基礎控除 3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続税の総額 14,800万円-4,800万円=10,000万円
妻の法定分に応じた相続税額
10,000万円×1/2=5,000万円
5,000万円×20%-200万円=800万円
子の法定分に応じた相続税額
10,000万円×1/4=2,500万円
2,500万円×15%-50万円=325万円
相続税総額
800万円+325万円×2=1,450万円
各自の負担税額
妻 1,450万円×1/2=725万円
子1 1,450万円×1/4=362.5万円
子2 1,450万円×1/4=362.5万円
配偶者の税額軽減により、妻の分の税額はゼロになります。
従って納税額は子2人分で
725万円です。先ほど計算した改正前の納税額は2人で445万円ですから、このケースでは280万円の増税になります。
いかがでしたでしょうか。相続税については説明すべきことが多いので,次回以降も引き続き相続税に関連したテーマでお伝えしていこうと思います。
<参考資料等>
・渡邉定義編「図解 相続税・贈与税」(大蔵財務協会)
・財務省ホームページ「平成25年度税制改正 資産課税」
 |
執筆者 |
| 在間 真太郎(ざいま しんたろう) | |
| 1963年生 50歳 | |
| 1986年中央大学商学部卒業後、小沢公認会計士事務所入所。 | |
| 1989年税理士試験合格、現在に至る。 | |
| 資産税案件、相続税案件を多数手掛ける。 |
-
実際にご利用された方の声をご参考ください。
-
気になる舞台裏をご紹介。
-
・コンサルティングサービス
お役立ち不動産コラム
相続税対策のご相談
売買に伴う税金無料相談
遊休地有効活用のご相談
底地借地問題のご相談
耐震性能や土壌汚染の診断
・仲介サポート
住宅ローンシミュレーター
住宅ローン
マンション設備検査・保証キャンペーン
損害保険
引っ越しサービス
ホームセキュリティ
不動産マーケット動向